税理士の平尾和也です。
今月も税金耳より情報を配信させていただきます。
今月は、経営者が知っておくべき「お金を貸す」相続対策の出口戦略と成功の秘訣というテーマです。
それでは、内容の要約です。

この対策は、親や祖父母から子や孫へ「お金を貸す(貸付金)」ことで、子や孫がその資金を有利に運用し財産を増やすことを目的とした、賢明な相続税対策です。
親族間の貸し借りでも、相続財産は「預貯金」から「貸付金」に形が変わるだけで、評価額は変わりません。
しかし、運用益を子や孫の世代に移せるのが最大のメリットです。
対策成功後の「出口戦略」:貸付金を誰が相続するか?
お金を貸した方(親や祖父母)が亡くなった際、貸付金という「債権」を誰が相続するかで、相続税の負担と借金の清算方法が変わります。
| 貸した人 | 借りた人 | 貸付金を相続する人 | 相続後の流れの結論 |
|---|---|---|---|
| 親 | 子 | 子 (借りた本人) | 子は貸付金(債権)を相続することで、自身の借金(債務)と自動的に相殺(混同)されます。子は貸付金に対して相続税を払いますが、返済義務は消滅します。 |
| 祖父母 | 孫 | 子 (祖父母の相続人) | 子が債権者となり、孫は子に借金を返済。最終的に子が亡くなり、孫が貸付金を相続することで相殺します。(時間をかけて税負担を移動) |
| 祖父母 | 孫 | 孫 (遺贈による) | 孫は貸付金(債権)を遺贈され、借金(債務)と相殺(混同)。孫は貸付金に対する相続税を払いますが、返済義務は消滅します。(早期に税負担を移動) |
ポイント: 最終的に借りた本人がその貸付金(債権)を相続すれば、民法の「混同」により借金(債務)の返済義務が消滅するという仕組みを活用します。これにより、子や孫に財産が残る効果を最大化します。
経営者として守るべき絶対ルール(税務否認を避けるため)
この対策の成功は、税務署に**「真の貸付け」であると認めてもらうかにかかっています。「貸付け」でなく「贈与」と認定されると、多額の追徴課税のリスクがあります。
1.「金銭消費貸借契約書」を必ず作成・保管する。
2.借入条件に基づき、利息を含め「実際に返済を行う」こと。
「書面なし」「返済の催促なし」は厳禁です。形式だけでなく実態も「貸付け」であることを証明できるようにしてください。
この方法は富裕層や地主の方だけでなく、資産規模に関わらず、将来の相続税対策として誰もが検討すべき有効な戦略です。
貸付け、または生前贈与(暦年贈与や相続時精算課税)のどちらが最適かはケースバイケースで検討が必要です。
当事務所では、こうした税制改正に対応するための対策についての相談以外にも 経営に悩む経営者様に向けて『経営お悩みコンサル』をはじめました。
売上をあげたい、採用したいけど人が来ない、人が定着しないなどのお悩みがない 経営者はごめんなさい、関係ないです。
そうでない方は、まずは45分の無料おためしコンサルもありますので、 ぜひみなさまのお悩みをお聞かせください。
日程調整はLINEでも可能です。ご連絡をお待ちしております。
会計事務所がこっそり教える税金耳より情報は、LINE公式で毎月配信中です。
毎月、最新情報のアップデートをしたい方はこちらからご登録ください。
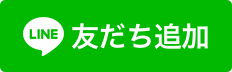


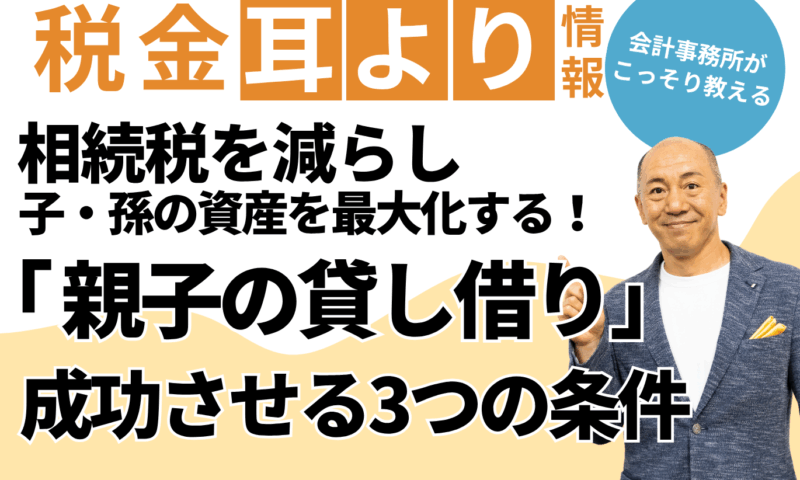
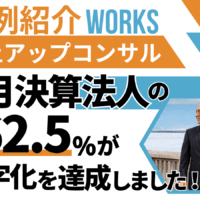
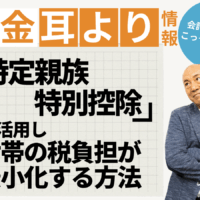
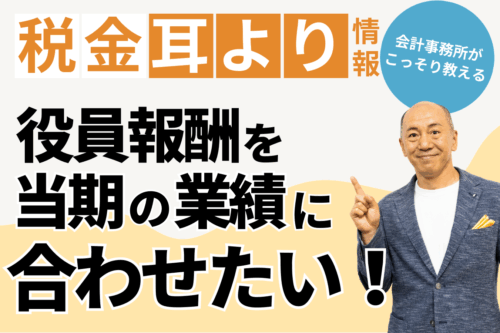
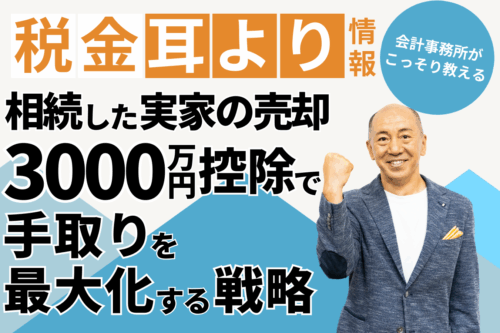

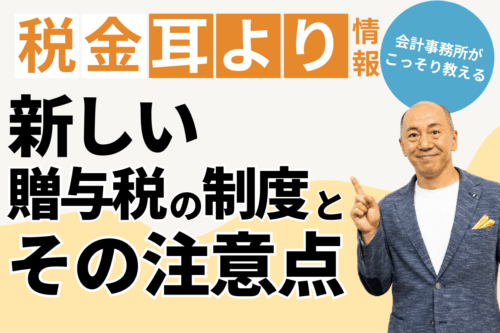
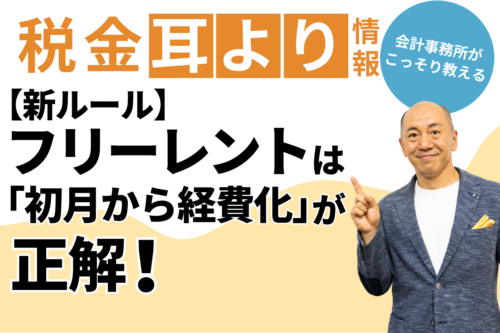
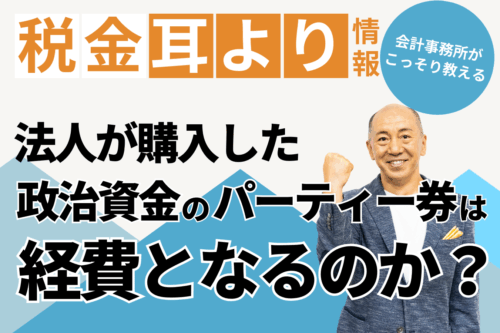


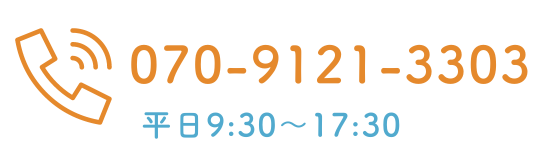


この記事へのコメントはありません。